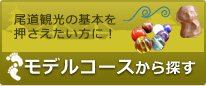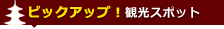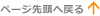おのなびの
おすすめ
ホーム > キーワード検索結果
キーワード検索結果
での検索結果
 熊箇原八幡神社 (くまがはらはちまんじんじゃ)
熊箇原八幡神社 (くまがはらはちまんじんじゃ)

(因島) 鎮座 仁和3(887)年。熊野大権現12神をはじめ多くの神々が祀られていて、因島の総氏神として崇められています。境内にある立派な土俵では毎年10月に奉納相撲大会が行われ、島内の子供や大人の力士による熱戦が行われます。 見性寺〔曹洞宗〕 (けんしょうじ)
見性寺〔曹洞宗〕 (けんしょうじ)

(因島) 曹洞宗天海山見性寺・大永7年(1527)大旦那田中右近により創建されました。本尊は薬師瑠璃如来。境内には因島八十八ヶ所霊場6番札所「安楽寺」があります。 向上寺〔曹洞宗〕 (こうじょうじ)
向上寺〔曹洞宗〕 (こうじょうじ)

(瀬戸田) 室町初期建立の曹洞宗のお寺です。潮音山(ちょうおんざん)の山頂にある国宝三重塔は、永享4年(1432)に建立されたもので、全体の高さは19mあります。和様唐様の混合様式で内部全体にも極彩色が施され、室町初期で最も美しく優れているものの一つに数えられています。日本画壇の巨匠 平山郁夫画伯も幼少のころよく遊ばれたそうです。 高根島灯台 (こうねじまとうだい)
高根島灯台 (こうねじまとうだい)

(瀬戸田) 明治27年5月15日に初点灯した当時の状態を良く残している石造りの灯台で、「日本の灯台50選」にも選ばれました。灯台からは三原の筆影山や因島、大三島など大パノラマを眺めることができます。 古浜児童公園 (こはまじどうこうえん)
古浜児童公園 (こはまじどうこうえん)

(市街地) 尾道の郊外にあるこの公園には引退した蒸気機関車のD51が屋外展示されています。1940(昭和15)年から1971(昭和46)年まで約30年間にわたり実際に運転していたもので、全走行キロは205万6000kmにも及びます。運転席の見学も可能です。 小林和作旧居 (こばやしわさくきゅうきょ)
小林和作旧居 (こばやしわさくきゅうきょ)

(市街地) 洋画家の小林和作(1888-1974、名誉市民)は1934年に東京より尾道へ転居し、晩年までこの地で活動しました。尾道へ転居後は市内はもとより、広島県内の美術界にも多くの功績を残し、現在でも多くの人に慕われています。その画風は山や海などの自然を赤や青を大胆に使い、優しく力強いタッチで描かれています。作品は尾道市立美術館にも所蔵されています。 金剛院〔真言宗〕 (こんごういん)
金剛院〔真言宗〕 (こんごういん)

(市街地) 西國寺の傑僧・慶鑁(けいばん)の開基と伝えられています。境内の裏には石で作られた三体の天狗の顔(重軽天狗)があり、これを願いをかけながら持ち上げ、軽く持ち上げることができると願いがかなうという言い伝えがあります。ほかにもお堂の中には「カラス天狗」のお面もあります。 金蓮寺〔曹洞宗〕 (こんれんじ)
金蓮寺〔曹洞宗〕 (こんれんじ)

(因島) 中世、瀬戸内で活躍した「村上水軍」の菩提寺です。境内の墓所には村上家やその家臣の石塔がずらりと並ぶほか、明治維新の元勲 鴻雪爪(おおとりせっそう)の墓もあります。また因島八十八ヶ所霊場第11番札所「藤井寺」があります。境内から見上げると村上水軍の貴重な資料を収めた因島水軍城を見ることができます。 西提寺〔曹洞宗〕 (さいだいじ)
西提寺〔曹洞宗〕 (さいだいじ)

(向島) 向島にある近代建築のお寺です。本尊は国の重要文化財に指定されている「聖観世音菩薩」。 済法寺〔曹洞宗〕 (さいほうじ)
済法寺〔曹洞宗〕 (さいほうじ)

(市街地) 宝暦3年(1753)広島国奉寺11世笑堂の開基と言われています。境内の山中の岩には釈迦や十六羅漢像など二十六尊者の石仏が刻まれています。またこの寺の9世物外(もつがい)不遷は「柔術不遷流」の開祖で多くの弟子を抱え、晩年は幕末動乱の中、平和を願い奔走し旅中に果てました。武術の他にも多くの俳句や書画を残し「拳骨和尚」として親しまれています。