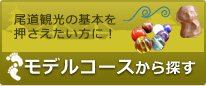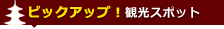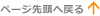おのなびの
おすすめ
ホーム > キーワード検索結果
キーワード検索結果
での検索結果
 住吉神社(浦崎) (すみよしじんじゃ(うらさき))
住吉神社(浦崎) (すみよしじんじゃ(うらさき))

(市街地) 尾道の東部、浦崎町に鎮座する神社。社伝では神功皇后が風浪の難を逃れるため浦崎町の磯間に避け、住吉大神を祀ったことにはじまるとされています。また平安後期の大般若経1巻(市重要文化財)を所蔵しており、時代的な特色を良く伝えています。10月第2週の土曜日になると、町内の神楽団により夜神楽が奉納され、夜更けまで多くの人々で賑わいます。 瀬戸内しまなみ海道 (せとうちしまなみかいどう)
瀬戸内しまなみ海道 (せとうちしまなみかいどう)

(全エリア) 「瀬戸内しまなみ海道」は西瀬戸自動車道の愛称で、本州・広島県尾道市と四国・愛媛県今治市の8つの島、9つの橋を全長約60kmで結ぶ架橋ルートです。このルートはそれぞれ形の異なった架橋で結んでいることから「橋の美術館」とも呼ばれています。このしまなみ海道の最大の特徴は、徒歩や自転車でも渡ることができること。特にCNNが選ぶ「世界で最もすばらしい7大サイクリングコース」にも選ばれ、世界屈指のサイクリングコースとして名をはせています。この海道を舞台にサイクリングの世界大会も開催され、世界中からサイクリストたちがやってきています。 瀬戸内しまなみ海道・新尾道大橋(尾道大橋) (せとうちしまなみかいどう・01しんおのみちおおはし(おのみちおおはし))
瀬戸内しまなみ海道・新尾道大橋(尾道大橋) (せとうちしまなみかいどう・01しんおのみちおおはし(おのみちおおはし))

(向島) しまなみ海道の本州側の起点の橋で、尾道と対岸の向島を結ぶ斜張橋です。新尾道大橋のすぐ隣には一般道の「尾道大橋」があり、双子の斜張橋として親しまれています。週末にはライトアップされ、尾道水道に浮かび上がります。この橋の下から見る尾道の街並みもおすすめです。 瀬戸内しまなみ海道・因島大橋 (せとうちしまなみかいどう・02いんのしまおおはし)
瀬戸内しまなみ海道・因島大橋 (せとうちしまなみかいどう・02いんのしまおおはし)

(因島) しまなみ海道で尾道側から2番目の「因島大橋」です。中央支間長770mは完成時には日本一の長さで、この橋を作るために培われた技術は以降の長大橋建設に大きな影響を与えました。橋は2層構造になっていて、下の部分は徒歩や自転車などでも通行することができます。隣接する大浜PAから歩いていくこともできるので、約1時間のお気軽な海上散歩を楽しむことができます。 瀬戸内しまなみ海道・生口橋 (せとうちしまなみかいどう・03いくちばし)
瀬戸内しまなみ海道・生口橋 (せとうちしまなみかいどう・03いくちばし)

(瀬戸田) しまなみ海道の尾道側から3番目の橋で、はっさくの島「因島」とレモンの島「生口島」を結ぶスタイリッシュな斜張橋です。この橋の特徴は支柱から陸上側が重いコンクリート桁、支柱より海側が軽い鋼桁と二つの材料を使い分けています。橋の下から見上げてみるとよく分かりますよ。 瀬戸内しまなみ海道・多々羅大橋 (せとうちしまなみかいどう・04たたらおおはし)
瀬戸内しまなみ海道・多々羅大橋 (せとうちしまなみかいどう・04たたらおおはし)

(瀬戸田) しまなみ海道の尾道側から4番目の橋で、広島県と愛媛県との県境にかかる斜張橋です。この橋はしまなみ海道で最後に開通した橋のひとつで(新尾道大橋、多々羅大橋、来島海峡大橋)、完成時には斜張橋として世界最長を誇りました。計画された当初は吊橋で造られる予定でしたが、瀬戸内海国立公園内に造られることから工事で景観の破壊が少ない斜張橋が選ばれました。この橋の主塔の真下では手を叩くとパーンと空に向かって反響する「鳴き竜」が体験できます。これはしまなみ海道ではこの橋だけのものです。 瀬戸内しまなみ海道・大三島橋 (せとうちしまなみかいどう・05おおみしまばし)
瀬戸内しまなみ海道・大三島橋 (せとうちしまなみかいどう・05おおみしまばし)

(市外) 愛媛県大三島と伯方島とを結ぶ全長328mのアーチ橋で、しまなみ海道の中では最初に架けられた橋です。橋が架かる海峡は「鼻栗瀬戸」と呼ばれ、最高7ノット(時速約13km)以上の速さで流れる海の難所の一つ。橋の上からは雄大な瀬戸内の風景をお楽しみいただけます。 瀬戸内しまなみ海道 伯方・大島大橋 (せとうちしまなみかいどう・06はかた・おおしまおおはし)
瀬戸内しまなみ海道 伯方・大島大橋 (せとうちしまなみかいどう・06はかた・おおしまおおはし)

(市外) 「伯方・大島大橋」は愛媛県伯方島と見近島とを結ぶ「伯方橋」と、見近島と大島とを結ぶ「大島大橋」とを総称した名前です。2本の橋の全長は1,165mで伯方橋は箱桁橋、大島大橋は吊り橋と、異なった形状の橋が連なっています。この橋が架かっている海峡は「宮窪瀬戸」と呼ばれ、激流のため海の難所として知られています。その海峡にある小島・能島は村上水軍本拠地のひとつ「能島水軍」が拠点として水軍城を築いていました。 瀬戸内しまなみ海道来島海峡大橋 (せとうちしまなみかいどう・07くるしまかいきょうおおはし)
瀬戸内しまなみ海道来島海峡大橋 (せとうちしまなみかいどう・07くるしまかいきょうおおはし)

(市外) 四国と愛媛県大島とを隔てる来島海峡に架かる橋で、「来島海峡第一大橋」~「来島海峡第三大橋」の3本の吊橋で構成されています。その全長は約4.1㎞にもおよび、その雄大な風景はしまなみ海道のなかでも随一のものです。また橋の下の来島海峡の潮流は最大10ノットにもなり、潮流体験も行われています。 瀬戸田サンセットビーチ〔しまなみレモンビーチ〕 (せとださんせっとびーち〔しまなみれもんびーち〕)
瀬戸田サンセットビーチ〔しまなみレモンビーチ〕 (せとださんせっとびーち〔しまなみれもんびーち〕)

(瀬戸田) 800mにもわたる白い砂浜と澄んだ青い海は中国地方でも屈指の海水浴場です。海水浴場のほか、キャンプ場などのレクレーション施設も充実しています。名前の通り夕日スポットとしても知られています。