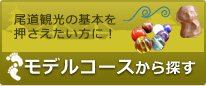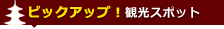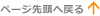おのなびの
おすすめ
ホーム > キーワード検索結果
キーワード検索結果
での検索結果
 信行寺〔浄土宗〕 (しんぎょうじ)
信行寺〔浄土宗〕 (しんぎょうじ)

(市街地) 建保2年(1214)、浄土宗第二祖の聖光が開いた寺で本尊は阿弥陀如来です。元は向島に草庵を結んで住み始めたのがはじめと言われています。正面石段の左側には「尾道志稿」の著者である油屋・亀山士綱の墓があり、右側には幕末維新のころ、尾道〜大阪間の船使を開いた回船問屋 竹内要助一門の墓があります。 慈観寺〔時宗〕 (じかんじ)
慈観寺〔時宗〕 (じかんじ)

(市街地) 貞治元年(1362)慈観上人の開基と言われています。4月末頃、庭には一面に牡丹が咲き“ぼたん寺”として親しまれています。また境内の片隅には「夫婦松」と呼ばれる松を見ることができます。これは2本の松が自然に絡まって成長した珍しいものです。 持善院〔真言宗〕 (じぜんいん)
持善院〔真言宗〕 (じぜんいん)

(市街地) 西國寺再興の傑僧・慶鑁(けいばん)の開基と伝えられています。再三の土砂災害に遭いましたが、そのたびに檀家や旦那衆などの協力により再建されました。お正月に配られる「干支の飾紙」は評判が高く、外国にまで送られるとか。 地蔵院〔曹洞宗〕 (じぞういん)
地蔵院〔曹洞宗〕 (じぞういん)

(因島) 因島八十八ヶ所の第24番札所「最御崎寺」があります。またお寺の墓地には江戸時代に碁聖として活躍した本因坊秀策の墓があり、囲碁ファンのお参りが途絶えません。 地蔵鼻 (じぞうはな)
地蔵鼻 (じぞうはな)

(因島) この鼻の地蔵さんに祈願し、娘の思いがこめられた小石を持ち帰ると恋が成就すると言われ、命日とされる毎月旧暦の24日には多くの若い女性が訪れます。また子授け、安産など女性の願い事がかなうといわれています。祈願がかなうと石地蔵を作り、お礼参りをする習慣があります。《由来は「詳しく」を参照下さい》 成願寺〔曹洞宗〕 (じょうがんじ)
成願寺〔曹洞宗〕 (じょうがんじ)

(因島) 文安の時代、宮地大炊助明光が因島庄山方に開創した仏通寺は臨在禅寺であったと伝えられており、天正10(1582)年に現在の場所に中興されました。また元禄5(1692)年に曹洞宗に改宗しました。お寺には室町期の毘沙門天の小像と桃山期の重井毘沙門堂本尊の木像が祭られていて、法楽踊の古いのぼりが遺されています。春はサクラで有名です。境内には因島八十八ヶ所霊場第12番札所「焼山寺」があります。 常称寺〔時宗〕 (じょうしょうじ)
常称寺〔時宗〕 (じょうしょうじ)

(市街地) 延慶2年(1309)、時宗第2世の他阿真教が諸国巡錫中、尾道にとどまり念仏弘通に勤めている際、霊夢を感じその地に生えていた榧(かや)の大木をもって一堂を建立したので榧堂と言われていたそうです。その後、焼失と再建を重ね、現在では山門と本堂の間に鉄道と国道が走り、山門は民家の中に残されています。また2007年には本堂や山門などが国の重要文化財に指定されました。 浄泉寺〔浄土真宗〕 (じょうせんじ)
浄泉寺〔浄土真宗〕 (じょうせんじ)

(市街地) 天文12年(1543)の創建と言われています。浄泉寺のシンボル、大屋根の上には畳16枚くらいの大きさの鬼瓦があります。また、境内にある用水桶は4匹の鬼が担いでいるユーモラスな姿を見ることができます。以前は縁側が広く涼しいため「昼寝寺」として親しまれていたとの逸話もあります。 浄土寺山展望台 (じょうどじやまてんぼうだい)
浄土寺山展望台 (じょうどじやまてんぼうだい)

(市街地) 千光寺山、西國寺山、と並び尾道三山に数えられる標高178.8mの浄土寺山頂上にある展望台です。尾道市内や眼下を斜めに横切る尾道水道、向島にある造船所やしまなみ海道沿線の島々を眺めることができます。頂上付近には展望台のほか、浄土寺奥の院や巨石群、抜群の展望を誇る不動岩などもあります。夕日や夜景スポットとしても知られ、キラキラと金色に輝く尾道水道は絶景です。 住吉神社 (すみよしじんじゃ)
住吉神社 (すみよしじんじゃ)

(市街地) 元文5年(1740)に尾道の町奉行に着任した平山角左衛門《名誉市民》は、翌年の寛保元年(1741)に住吉浜を築造し尾道発展の基礎を築きました。その際、浄土寺境内にあった住吉神社をこの住吉浜に移して港の守護神としました。毎年旧暦の6月28日前後の土曜日、平山奉行の功績を称えるためおのみち住吉花火まつりが開催され、尾道の夏の風物詩になっています。