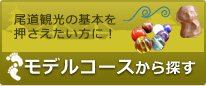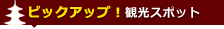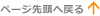おのなびの
おすすめ
ホーム > キーワード検索結果
キーワード検索結果
での検索結果
 (4月第1日曜日)名荷神楽奉納 ((04月第1日曜日)みょうがかぐらほうのう)
(4月第1日曜日)名荷神楽奉納 ((04月第1日曜日)みょうがかぐらほうのう)

(瀬戸田) 室町時代に起こった疫病や干ばつを鎮めるため、島民が神楽を奉納したことに始まる神楽。御幣や扇子を持ち神楽を舞い、五穀豊穣や家内安全を祈ります。伝統の舞を現在に受け継いでおり、1968年(昭和43年)、広島県無形民俗文化財に指定されています。 (5月上旬)尾道薪能 ((05月上旬)おのみちたきぎのう)
(5月上旬)尾道薪能 ((05月上旬)おのみちたきぎのう)

(市街地) 国宝の寺・浄土寺の重要文化財、阿弥陀堂を舞台に能や狂言が演じられます。薪の燃える灯りの中披露される優雅な舞を心ゆくまで堪能 してください。 (6月下旬)あじさいき ((06月下旬)あじさいき)
(6月下旬)あじさいき ((06月下旬)あじさいき)

(市街地) 「放浪記」の作者で、幼少時代の多感な時期を尾道で過ごした林芙美子。彼女の命日にちなみ、商店街入り口にたたずむ林芙美子像前にて地元の学生たちによる合唱や演奏、「放浪記」の朗読のほか、あじさいの献花などが行われます。 (6月下旬)大山神社天神夏越祭 ((06月下旬)おおやまじんじゃてんじんなごしさい)
(6月下旬)大山神社天神夏越祭 ((06月下旬)おおやまじんじゃてんじんなごしさい)

(因島) 大山神社の天神祭と夏越のお祓い神事です。ボケ封じを祈願する「茅の輪くぐり」をはじめ、あかちゃんがどちらが早く泣くかを競う「泣き相撲」などユニークなイベントも開催されます。 (6月下旬)祇園祭 ((06月下旬)ぎおんまつり)
(6月下旬)祇園祭 ((06月下旬)ぎおんまつり)

(市街地) 久保八坂神社の例祭で尾道の三大夏祭りのひとつにも数えられています。2日目には3体の神輿が幟の周りを駆け回り、その時間を競うタイムトライアルや「三体廻し」が行われ、会場は男たちの熱気で包まれます。 (6月中旬~7月下旬の土曜日)土曜夜店 ((06月中旬~07月下旬の土曜日)どようよみせ)
(6月中旬~7月下旬の土曜日)土曜夜店 ((06月中旬~07月下旬の土曜日)どようよみせ)

(市街地) 6月~7月の土曜日の夜、尾道本通り商店街を約1㎞にわたり昔懐かしの綿菓子や金魚すくいなどの屋台が立ち並び、多くの人出で賑わう尾道の夏の風物詩。夏の夜、浴衣に身を包んでのんびり屋台めぐりを楽しんでみてはいかが? (7月下旬)水尾町の水祭り ((07月下旬)みずおちょうのみずまつり)
(7月下旬)水尾町の水祭り ((07月下旬)みずおちょうのみずまつり)

(市街地) 江戸時代からの歴史を持ったお祭で、尾道の夏の風物詩です。時事ネタやテーマに沿った場面を細工人形で表現し、その人形の指先などから噴水が出る涼しげなお祭です。様々な風刺や昔話などを人形で表現しています。 (7月下旬)宮島さん協賛 いんのしま水軍花火大会 ((07月下旬)みやじまさんきょうさんいんのしますいぐんはなびたいかい)
(7月下旬)宮島さん協賛 いんのしま水軍花火大会 ((07月下旬)みやじまさんきょうさんいんのしますいぐんはなびたいかい)

(因島) 因島の夏を彩る花火まつりです。土生港の沖合に浮かぶ鶴島付近より約3,000発の花火が、息をつく暇もなく次から次へと打ちあがります。大玉の花火やスターマイン、100連発や200連発の煙火花火などをお楽しみ下さい。 (7月中旬)天神祭 ((07月中旬)てんじんまつり)
(7月中旬)天神祭 ((07月中旬)てんじんまつり)

(市街地) 御袖天満宮の夏祭り。映画「転校生」の階段落ちでも有名な石段を神輿が上り下りする「勇壮五十五段大神輿還幸の儀(最終日)」や福引大会、大道芸などが行われます。迫力満点のお祭をお楽しみください。 (8月18日(西暦の偶数年))吉和太鼓踊り ((08月18日)よしわたいこおどり)
(8月18日(西暦の偶数年))吉和太鼓踊り ((08月18日)よしわたいこおどり)

(市街地) 足利尊氏の戦勝の祝いとして始めたものが起源とされています。市内を浄土寺まで尊氏の御座船をかたどった神輿と共に太鼓を打ち鳴らしながら踊り、浄土寺に踊りを奉納します。《まつりの起源については「詳しく」参照》