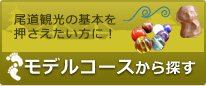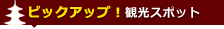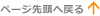おのなびの
おすすめ
ホーム > キーワード検索結果
キーワード検索結果
での検索結果
 覚明神社 (かくめいじんじゃ)
覚明神社 (かくめいじんじゃ)

(向島) 元暦元年(1184)、信濃源氏の武将である木曽義仲(源義仲)が江州栗津ヶ原で源義経に討たれた際、家臣の大夫坊覚明は義仲の子である義重と家臣30名余りを伴って現在神社がある覚明島(現:向島・川尻地区)に移り住んだと伝えられています。移住後、寺社の再建・土地の開墾・治水灌漑などに尽力した後、家臣らの自立を見届けた覚明と義重は信州へと帰って行きました。この神社はその覚明や、木曽義仲、義重を祀ったものです。 兼吉の丘 (かねよしのおか)
兼吉の丘 (かねよしのおか)

(向島) 尾道の対岸・向島の小高い丘で「兼吉の丘」と呼ばれています。この場所からは尾道の町並みや尾道水道を行き交う渡船、夜景など尾道らしい風景を楽しめます。また春には丘の中腹に咲き誇る桜越しの風景は格別です。丘の頂上部分は大林宣彦監督の新・尾道三部作「あした」のロケ地となっています。 蒲刈小早川氏五輪塔 (かまがりこばやかわしごりんとう)
蒲刈小早川氏五輪塔 (かまがりこばやかわしごりんとう)

(因島) 柑きつ畑をしばらく進むとひっそりと石が積まれた場所があります。これは康永3年(1344)~応永年間(1394~1427)までの83年間に渡りこの地を支配した蒲刈小早川氏の墓と言われる五輪塔です。この五輪塔のある一帯は小早川氏の居城、鶴ヶ峰一ノ城の屋敷跡で、城跡は徒歩で10分ほどの山中にあります。五輪塔の横には子孫が建立した「蒲刈小早川先栄城」の碑が建立されています。 亀の首地蔵 (かめのくびじぞう)
亀の首地蔵 (かめのくびじぞう)

(瀬戸田) 生口島と高根(こうね)島との間の瀬戸田水道に建立されているお地蔵さんで、航海の安全を見守っています。名前の由来は、昔この一帯で人を食べていた亀を退治した際、首が海に落ち、亀のような岩になったとの言い伝えによります。潮が引くと地蔵の下に亀の形をした岩が現れます。《亀の首地蔵伝説は「詳しく」参照》 亀森八幡神社 (かめのもりはちまんじんじゃ)
亀森八幡神社 (かめのもりはちまんじんじゃ)

(向島) 宝亀元年(770年)、現在の向島・兼吉地区に山陽道巡察使 藤原百川豊前国宇佐宮の御分霊を勧請したことに由来する神社です。1月14日に開催される「とんど祭」、10月第4金曜日に開催される「オハキ神事」は、尾道市無形民俗文化財に指定されています。境内にある「除虫菊神社」は、除虫菊を日本に紹介し当地で栽培を奨励した大日本除虫菊(株)初代社長・上山英一郎が祀られており、毎年5月8日に例祭が執り行われます。 亀山八幡宮(久保八幡神社) (かめやまはちまんぐう(くぼはちまんじんじゃ))
亀山八幡宮(久保八幡神社) (かめやまはちまんぐう(くぼはちまんじんじゃ))

(市街地) 亀山八幡宮(久保八幡神社)は、貞観年間(859年~877年)の創建と伝えられています。境内には尾道の石工が彫り上げた「軍配灯籠」と呼ばれる軍配が彫られた灯籠や狛犬、そして江戸時代の横綱陣幕久五郎の手形が入った石碑などが点在しています。1月には「とんど祭」、秋には「わんぱく相撲大会」も開催されています。 観音山(火瀧山) (かんのんやま(ひたきさん))
観音山(火瀧山) (かんのんやま(ひたきさん))

(瀬戸田) 標高472.3m、生口島はもとより、芸予諸島の最高峰となっています。頂上からは愛媛県の伯方島や大島などの島々や、遠く四国山地まで大パノラマを一望できます。別名「火瀧山」とも呼ばれ、その昔この山で狼煙を上げていたことに由来します。また雨乞い祈祷の霊場としても知られ、毎年4月の第2日曜日には火瀧観音大祭が営まれます。 冠天神 (かんむりてんじん)
冠天神 (かんむりてんじん)

(向島) 901年に菅原道真が大宰府に流される際、ここに訪れ、境内にある大岩にかぶっていた冠を置いたとの言い伝えが残っており、そのことが名前の由来となっています。そのほか1900年に勃発した「義和団の乱」で使用された砲弾が残されています。 吉備津彦神社(一宮神社) (きびつひこじんじゃ(いっきゅうじんじゃ))
吉備津彦神社(一宮神社) (きびつひこじんじゃ(いっきゅうじんじゃ))

(市街地) この神社は尾道では「一宮(いっきゅう)さん」として親しまれています。11月1日~3日にかけて行われる例祭の「尾道ベッチャー祭り」は秋の尾道を代表するお祭で、最終日に行われる練り歩きはこの祭りのハイライトです。太鼓やお囃子とともに「ベタ」「ソバ」「ショーキー」の3体の鬼が市内へ繰り出し、その鬼たちが手に持つササラや祝棒で観衆らをたたいたり突いたりしながら厄除けを行います。この奇祭は尾道市無形民俗文化財に指定されています。 旧出雲街道跡(銀山街道「宇根の古道」) (きゅういずもかいどうあと(ぎんざんかいどう「うねのこどう」))
旧出雲街道跡(銀山街道「宇根の古道」) (きゅういずもかいどうあと(ぎんざんかいどう「うねのこどう」))

(御調) 旧出雲街道は江戸時代初期に大久保長安により整備された道路で、世界遺産に登録された石見銀山から尾道への銀の輸送や、米の運搬など山陰と山陽とを結ぶ大動脈として機能しました。幅は7尺(約2.1m)で1610年代に完成したと伝えられています。現在ではその一部のみが現存しており、この「宇根の古道」もそのうちのひとつです。